【買取】文房清玩(二玄社)│書道の本を売るなら忠益軒チュウエキケンへ!
【買取】文房清玩(二玄社)│書道の本を売るなら忠益軒チュウエキケンへ!
中田勇次郎先生の名著、『文房清玩』(二玄社)全5冊を入荷いたしました。
書道の本などで見かけることの多い文房清玩という言葉は、どういう意味の言葉なのか。中田先生の『文房清玩』は、どのような本なのか。
この記事では、文房清玩の意味、二玄社から出版された『文房清玩』の内容などについて解説します。
文房清玩の意味
「文房清玩とは、○○である。」
辞書のように、明確に言い切りたいところですが、そうはいかないのが「文房清玩」という言葉の難しさです。
試しに、「文房」と「清玩」というように二つの単語に区切って、それぞれの意味を合わせることによって「文房清玩」という言葉の意味を考えてみましょう。
文房とは、「書物を読んだり、物を書いたりするためのへや。書斎。」を意味します。もう一方の清玩は、「清らかな鑑賞の対象となる物。」を意味します。1
二つの単語の意味を合わせれば、おおよそ「書斎にある清らかな鑑賞の対象となる物」、または「書斎で清らかな物を鑑賞する行為」を意味するということになりそうです。
たしかに間違いではありません。清潔な書斎で書画骨董を愛玩する、まさに「文房清玩」と名付けたくなる様子です。しかし、何かが足りない。そう感じる人もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、ここでは「文房清玩」という言葉を次のような言葉だと考えてみたいと思います。
明るい窓のもと、机などの家具を清潔に保ち、書や絵画、あるいは古代の青銅器のような器物、または庭の草花や瓶に挿してある花卉を鑑賞愛玩する。趣味を同じくする友人がいれば、茶を飲みながら、あれこれと話もはずむ。日々の仕事、隣近所や家族間での些細な争い、そのような俗世間からは離れた空間がそこには生まれる。こんな空間にある物、漂う空気や雰囲気、そしてそこから発生した境地、これらをまとめて表現したのが「文房清玩」という言葉である。
長くなってしまいましたが、ここで言いたかったことは、「文房清玩」という言葉が特定の物や状況を指すだけでなく、かなり幅広い意味を持つ言葉だということです。
そんな「文房清玩」に、中国や日本の文人たちは憧れの気持ちを持ってきました。
二玄社の『文房清玩』はどんな本?
さて、そのように幅広い意味を持つ「文房清玩」という言葉が表現するものを知るにはどうしたらよいでしょうか。そんなときに役立つのが、本書『文房清玩』全5冊セットです。
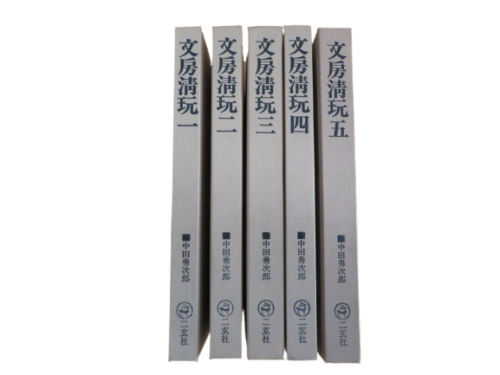
二玄社から刊行された『文房清玩』には、宋時代以降に中国で書かれた文房清玩についての文献の翻訳、また中田勇次郎先生の書いた文房清玩に関する論考などが収録されています。
簡単に、全巻の収録内容を見てみましょう。
第一巻
□山家清事(宋・林洪) □負喧野録(宋・陳槱) □洞天清禄集(宋・趙希鵠)
第二巻
□考槃余事(明・屠隆)
第三巻
□梅譜(宋・范成大) □洛陽牡丹記(宋・欧陽脩) □瓶史(明・袁宏道) □中国における挿花の習俗(中田勇次郎) □硃砂魚譜(明・張謙徳) □間情偶寄 居室器玩部(清・李漁)
第四巻
宋人硯譜十種 □硯譜(欧陽脩) □硯記(蔡襄) □硯録(唐詢) □歙州硯譜(唐積) □歙硯説(無名氏) □弁歙石説(無名氏) □硯史(米芾) □端渓硯譜(無名氏) □硯譜(無名氏) □硯譜(李之彦) □蜀牋譜(元・費著)
第五巻
□文房清玩史考 □文房雑記
いかがでしょうか?
この収録内容を見ても、文房清玩が、単に古い物を愛玩することだけを意味するのではないと推測できるのではないでしょうか。
第一・二巻は、文房清玩についての意識が盛んだったころ、すなわち宋代と明代の文献を収録しています。
「洞天清禄集」や「考槃余事」は、宋時代や明時代に記された文房清玩についての代表的な文献です。これらを読むことによって、当時の文人が文房清玩をどのように考えていたのか、その一端を知ることができるでしょう。
第三・四巻は、文房清玩を構成する物について解説した文献、いわば文房清玩の各論です。
文房清玩を語るときに、硯・青銅器・花卉など、書斎を彩る器物の存在を欠かすことはできません。そんな器物について、具体的に説明している文献を収録しています。
特に、文房四宝の一つとして大切にされてきた硯(スズリ)についての文献と、画や詩の題材として愛されてきた花卉についての文献が充実しています。
第五巻は、中田先生の書いた文房清玩に関する論考を収録しています。
文房清玩についての考えは、長い中国の歴史の中で、少しずつ養われ発展してきました。各時代の文献を読むのも楽しみですが、なかなか骨の折れる作業です。
そこで活用したいのが本巻です。古今の文献を基礎にした幅広い知識を持つ中田先生の書いた論考を読めば、「文房清玩」というものがどのように考えられてきたのか、そのあらましを知ることができるでしょう。
本巻は文房清玩についての概説書ということもできるのではないでしょうか。
翻訳作品には、中田先生による詳しい解説と註が付いているので、大変参考になります。
碩学・中田勇次郎
さて、中田勇次郎先生について簡単に紹介しておきましょう。
中田先生は、明治38年(1905年)、京都で繊維問屋を営む家に生まれました。生家が裕福であったため、恵まれた環境で教育を受けることができ、高等学校卒業後、京都大学で中国文学を学びました。
京都大学といえば、内藤湖南、桑原隲蔵、狩野君山など、わが国を代表する中国学者が数多く教員として在籍していたことで有名です。中田先生も、青木正児や鈴木虎雄といった人々に指導を受けたそうです。
大学院を卒業すると、早くから大谷大学の教授となり、京都市立芸術大学など複数の大学で教鞭をとりました。
中田先生は幅広い分野で業績を残しましたが、特に、中国の文章の一形式である「詞」と書道史についての研究で高く評価されています。
中田先生の書いた『王羲之を中心とする法帖の研究』(二玄社)、『中国書論集』(二玄社)、『文人画論集』(中央公論社)などの本を愛読したという方も、書道に関心を持つ人のなかにはいらっしゃることでしょう。
また、現在でも人気の高い『文人画粋編』や『欧米収蔵 中国法書名蹟集』などの編集にも携わっていました。
現在では、中田先生の業績をまとめた『中田勇次郎著作集 心花室集』が二玄社から出版されています。2
『文房清玩』を読んで、文人の境地を体験してみましょう!
昔の文人が体験したような文房清玩の境地を、私たちも同じように体験するということは、大変難しいことなのかもしれません。
明窓浄机(明るい窓に清らかな机)は用意できても、何百万円もする硯や何億円もする青銅器を手元に置くことは、多くの人には困難です。さらに、趣味を同じくする友人と出会うことも、高価な器物を手に入れるのに劣らないほど難しいことでしょう。
しかし、文房清玩の境地を味わいたいという願望を持っている人は、現在でも少なくないと思います。
そこで、残されている文献を読んで、先人たちの境地を追体験するというのはいかがでしょうか。高価な品物を手元に置き、同じ趣味の友人とその場を共有することに比べれば、読書のほうが手軽にできるでしょう。
「本でも読んで文人の境地を味わってみるか」とお考えの方は、ぜひ、中田先生の書いた『文房清玩』を読んでみてください。中国の文人たちがどのような世界に憧れ体験したのか、そんなことを知るために最適の本です。
【買取情報】書道本や書道用品など、書道に関するもの買取りいたします
さて、忠益軒では書道本や書道用品など書道に関するもの全般を買取りいたしております。
また書道以外のジャンルの古本古書も買取りいたします。
こんなものの処分でお悩みではありませんか?
古本古書 最新刊から戦前の本まで、専門書から趣味の本まで幅広く対応しております
◎哲学 ◎思想 ◎宗教 ◎神道 ◎仏教 ◎キリスト教 ◎イスラム教 ◎ユダヤ教 ◎美術・芸術 ◎建築 ◎彫刻 ◎工芸 ◎絵画 ◎写真 ◎音楽 ◎演劇 ◎日本文学 ◎世界文学・海外文学 ◎語学 ◎国語学 ◎書誌学 ◎古典文学 ◎国文学 ◎政治 ◎経済 ◎法律 ◎社会 ◎教育 ◎武道 ◎世界史 ◎日本史 ◎国学 ◎考古 ◎地理 ◎民族学 ◎民俗学 ◎科学 ◎数学 ◎物理 ◎化学 ◎天文 ◎工学 ◎生物 ◎心理 ◎医学 ◎東洋医学 ◎漢方 ◎鍼灸 ◎整体 ◎洋書 ◎限定本 ◎署名本・サイン本 ◎初版本 ◎肉筆原稿 ◎名家書簡・色紙
江戸時代以前の本 糸でとじてある本は江戸時代以前の本の可能性があります
◎和本 ◎唐本 ◎朝鮮本 ◎越南本 ◎巻子本・巻物 ◎古写本 ◎古版本 ◎春日版 ◎高野版 ◎五山版 ◎古活字版 ◎絵巻 ◎奈良絵本 ◎丹緑本 ◎特製本 ◎献上本 ◎仏書・仏典 ◎お経 ◎写経 ◎経書 ◎史書 ◎有職故実 ◎詩集 ◎歌集 ◎句集 ◎草双紙 ◎青本 ◎赤本 ◎黒本 ◎黄表紙 ◎読本 ◎合巻 ◎戯作 ◎洒落本 ◎人情本 ◎滑稽本 ◎地誌 ◎名所図会 ◎道中記 ◎武鑑 ◎吉原細見 ◎浮世絵・錦絵や番付その他の紙もの ◎その他
書道用品・書道具や書道本 書道についてのものなら、まとめて査定買取りいたします
◎墨 ◎紙 ◎筆 ◎硯(スズリ) ◎水滴 ◎印材 ◎印譜 ◎拓本 ◎篆刻用品 ◎お手本 ◎法帖 ◎水滴 ◎筆筒 ◎墨床 ◎腕枕 ◎古筆切 ◎短冊 ◎掛け軸 ◎まくり ◎名家書作品 ◎台北・故宮博物院の名蹟(二玄社複製品) ◎その他
思い当たるものがございましたら、ぜひ忠益軒へご連絡ください。
本の出張買取・宅配買取は忠益軒チュウエキケンにお任せください!
忠益軒では、出張買取または宅配買取でお客様から品物を買取りいたしております。
出張買取について
出張買取は、当店スタッフが品物のある場所を訪問して、査定や運び出しをする買取方法です。
当店スタッフが直接訪問するため、品物を梱包したり縛ったりするお客様の手間は一切かかりません。
査定完了後、金額の提示をし、お客様にご了承をいただきましたら、そのまま運び出し作業を行います。
ご依頼のご連絡後、お客様に負担がほとんどない人気の買取方法です。
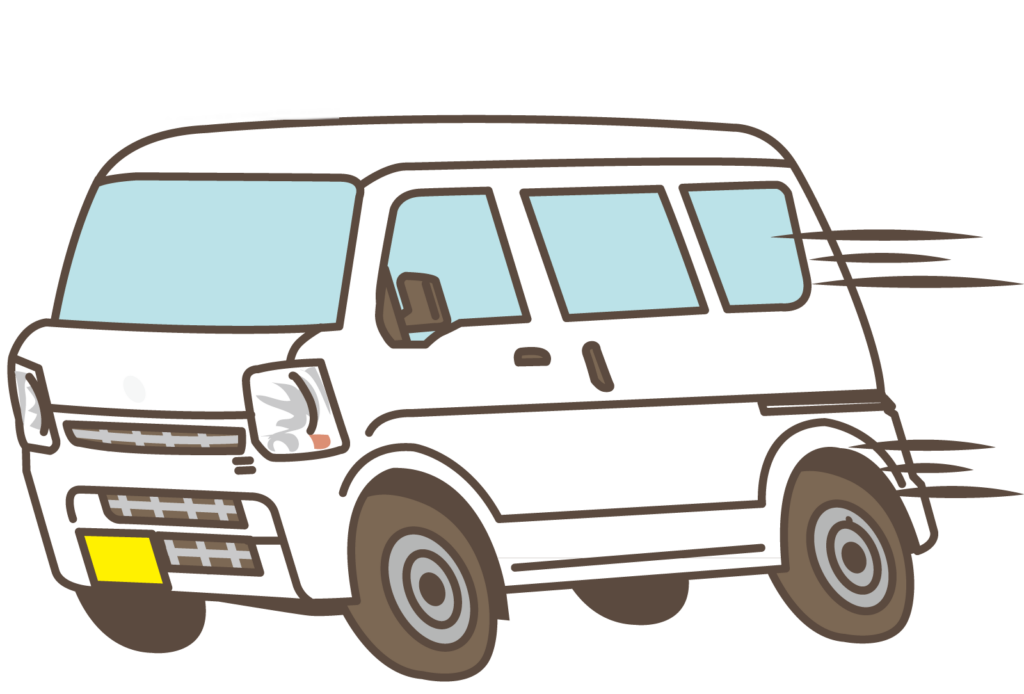
宅配買取について
宅配買取は、お客様から品物を送っていただき査定する買取方法です。
全国どこからでも受け付けているため、遠方のお客様にも人気のある買取方法です。
また、忙しくてなかなか出張を依頼できないというお客様からもご好評をいただいております。
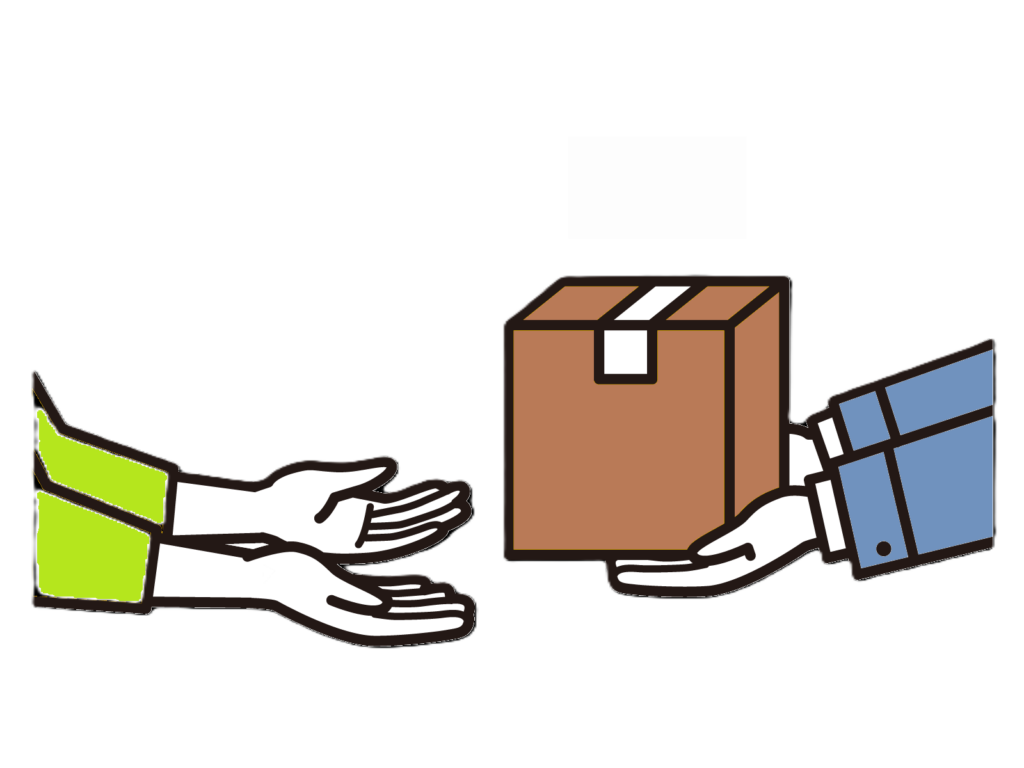
まとめ
まとめ
☆「文房清玩」という言葉は、特定の物を指すだけでなく、雰囲気や境地なども意味する広い意味の言葉
☆『文房清玩』中田勇次郎(二玄社)全5冊は、文房清玩についての文献や中田先生の論考を収録した本
☆中田勇次郎は、書道史などの研究で大きな功績があり、著書や編著も多数残している
☆中田先生の『文房清玩』全5冊は、文房清玩の意味するところを知りたい人が読むのに最適な本

お問い合わせ
買取りのご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください


